- シーンから探す
-
贈る相手から探す
- 彼氏
- 彼女
- 男友達
- 女友達
- 夫・旦那
- 妻・奥さん
- お父さん・父
- お母さん・母
- 両親
- おじいちゃん・祖父
- おばあちゃん・祖母
- 女性
- 男性・メンズ
- 妊婦
- 同僚
- 同僚(男)
- 同僚(女)
- 上司(男)
- 上司(女)
- 部下
- ビジネスパートナー・取引先
- 夫婦
- カップル
- 親友
- 女の子
- 子供
- 男の子
- 赤ちゃん・ベビー
- 乳幼児
- 1歳の誕生日プレゼント
- 2歳の誕生日プレゼント
- 3歳の誕生日プレゼント
- 4歳の誕生日プレゼント
- 5歳の誕生日プレゼント
- 6歳の誕生日プレゼント
- 7歳の誕生日プレゼント
- 8歳の誕生日プレゼント
- 9歳の誕生日プレゼント
- 10歳の誕生日プレゼント
- 18歳の誕生日プレゼント
- 19歳の誕生日プレゼント
- 20歳の誕生日プレゼント
- 21歳の誕生日プレゼント
- 22歳の誕生日プレゼント
- 25歳の誕生日プレゼント
- 26歳の誕生日プレゼント
- 30歳の誕生日プレゼント
- 40歳の誕生日プレゼント
- 50歳の誕生日プレゼント
- 60歳の誕生日プレゼント
- 70歳の誕生日プレゼント
- 80歳の誕生日プレゼント
- 88歳の誕生日プレゼント
- 90歳の誕生日プレゼント
-
カテゴリから探す
- 名入れギフト
- 記念品
- 文房具
- 花
- ビューティー
- こだわりグルメ
- ジュース・ドリンク
- お酒
- 絶品スイーツ
- ケーキ
- お菓子
- プリン
- フルーツギフト
- リラックスグッズ
- アロマグッズ
- コスメ
- デパコス
- インテリア
- キッチン・食器
- グラス
- 家電
- ファッション
- アクセサリー
- バッグ・ファッション小物
- ブランド腕時計(メンズ)
- ブランド腕時計(レディース)
- ベビーグッズ
- キッズ・マタニティ
- カタログギフト
- 体験ギフト
- 旅行・チケット
- ダレスグギフト
- ペット・ペットグッズ
- 面白い
- 大人向けのプレゼント
- 贅沢なプレゼント
- その他ギフト
- プレゼント交換
- 絆ギフト券プロジェクト
- リモート接待・5000円以下
- リモート接待・8000円以下
- リモート接待・10000円以下
- リモート接待・10000円以上
- おまとめ注文・法人のお客様
【茶器/茶道具 抹茶茶碗】 黒楽茶碗 眞清水福山作 数印 銘「看々」 高田明甫付:いまや茶の湯日本茶・今屋静香園
-
商品説明・詳細
-
送料・お届け
商品情報
残り 1 点 163,900円
(167 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 08月17日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)
-
ラッピング
対応決済方法
- クレジットカード
-

- コンビニ前払い決済
-

- 代金引換
- 商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥299,000 まで対応可能)
- ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
-
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行 - Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)
-






















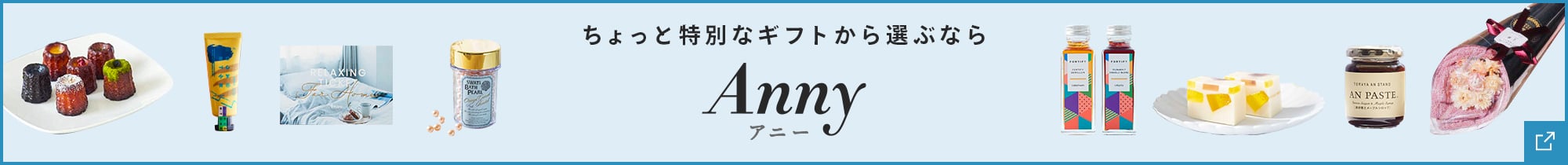




1843年天保14年 京都五条坂に開窯して眞清水蔵六と改名する
1868年明治初年 政府の奨励をうけて外国の博覧会に出品して名をあげ、国内向けには茶器、外国向けには色絵・金襴手の大作を発表、製作する
青磁・染付などを製作
千宗室が孝明天皇への献茶の折「宗岳」の名を賜られた
印は「宗岳」「百寿」「蔵六」等
【2代 蔵六】(1861-1936 76才没)
1882年明治15年 2代を襲名
1884年明治17年 京都博覧会にて一等金賞を受賞する
1912年大正元年 沢中庵と号する
1917年大正06年 京都山科西野山に開窯
1926年昭和元年 ご大典の際、青磁香炉を謹製する
内外陶磁の造詣深く、中国陶磁の写しに優品多数。
【3代 蔵六】(1905-1971)
【4代 蔵六】(1933-)
1933年昭和08年 3代に長男に生まれる
1956年昭和31年 関西美術学院修了の後、父に師事し作陶を始める。青磁、三島、粉引、刷毛目など幅広く手掛ける
1971年昭和46年 4代 蔵六を襲名
【5代 蔵六 (本名 徹)】玄々窯
1962年昭和37年 4代眞清水蔵六の長男として京都に生
1984年昭和59年 京都府立陶工高等技術専門校専攻科終了
1985年昭和60年 唐津 西岡小十市に師事、父の4代蔵六に師事し作陶に専念
1993年平成05年 金閣寺大書院壁画完成記念茶碗謹製
1998年平成10年 唐津にて割竹式登り窯(玄々窯)開窯
------------------------------
【眞清水福山(本名 伸)】
1966年昭和41年 4代 眞清水蔵六の次男として京都に生
1986年昭和61年 京都府立高等技術専門校専攻科を終了
1987年昭和62年 京都市立工業試験場修了
4代 父蔵六に師事
1993年平成05年 金閣寺大書院壁画完成記念茶碗謹製、、個展・父子展の他、西岡小十に師事する兄の玄々窯:眞清水徹と二人展など
2009年平成21年 大徳寺管長:嶺雲室、高田明甫宗哲老師より、「亀禄窯」の窯銘を賜る
瑞峰院 前田昌道老師より「福山」の号を受ける
楽家の初代長次郎が千利休の創意を受けて造った茶碗で黒楽の釉・けずりで形を整えた!!
熱を伝えにくい土の美・お湯が冷めにくい性質と色彩的にも緑の写り具合が大変よく、まさにお茶のために作られた茶碗。
<五山の口造りで幽玄の世界を表現>しています。
利休の命により、初代長次郎が作った理想の茶碗であり、二代目常慶が豊臣秀吉より楽の字の印を賜わる。楽家の脇窯の一つに金沢の大樋焼(飴楽)があります。現在多くの陶芸家による写し物の茶碗がある。
成形のぐあいを作行きといい、まず手にとって眺めて全体を見る、感じることが大切。
作者印のある高台は見どころの要です。土味は土の色合い。硬軟を知り陶工の手腕をあらためます。
井戸茶碗をはじめ高麗茶碗や唐津に多い竹節高台や三ヶ月高台や割高台がある。